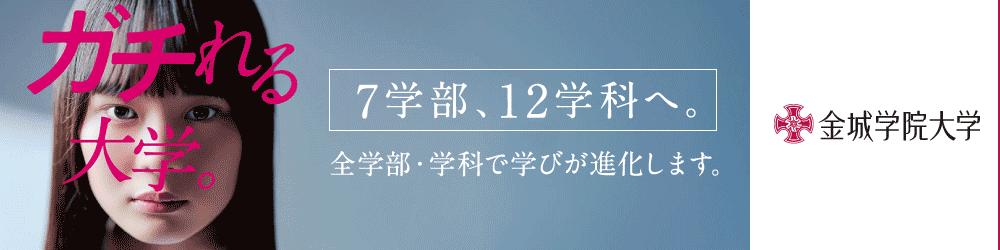東海・北陸の医学・歯学・薬学・看護・リハビリが学べる私立短大一覧
-
- 資料請求カートに追加(送料とも無料)
- 資料請求キャンペーン対象
-
 私立短期大学 | 三重県
私立短期大学 | 三重県高田短期大学
保育・幼児教育・ビジネス・介護福祉のやりがいを学び、資格と技術で確かな就職力と実践力を身につける
高田短期大学では、保育士・幼稚園教諭二種免許状・介護福祉士の国家資格をはじめ、多数のビジネス系の資格取得を目指せます。(※) また、多数の卒業生が業界で活躍中。徹底した就職サポートで地元『三重県』での就職に強い学校です。 ■就職に強い 就職率98.7%*(2022~2024年3月実績)。就職支援サービスと卒業生ネットワークで地元就職を強力にバックアップ ■施設・設備が充実 充実した学びのための専門施設が多数。快適なキャンパスライフが楽しめます。 ※厚生労働省「指定保育士養成施設一覧(令和4年4月1日時点) 」No.214参照 文部科学省「幼稚園教員の免許資格を取得することのできる大学」〔1〕通学課程(2)二種免許状(短期大学卒業程度) 参照 厚生労働省「介護福祉士養成施設一覧」No.287参照 *(就職希望者数701名/就職者数692名)
- 資料請求カートに追加(送料とも無料)
- 資料請求キャンペーン対象
-
私立短期大学 | 富山県
富山福祉短期大学
私が変わる。未来が変わる。
富山福祉短期大学(ふくたん)は、1997年創立の福祉を広く学ぶことのできる総合短期大学です。「社会福祉学科」「看護学科」「幼児教育学科」に加え、2022年4月には「専攻科看護学専攻」を開設しました。 少子高齢化や地域のつながりが強く求められる時代、専門的な知識と実務経験を持つ講師陣の授業と実践を交えたカリキュラムで学びを深めます。また、「福祉」を学ぶ人材として、人としての素養・教養を高め、学生それぞれの個性・自主性を重視し、実践躬行をもって人々のより豊かな生活、良き社会の形成に自分から貢献できる人材を育成します。 また、多様な学びを支援しており、全国の短期大学でもめずらしい長期履修制度を活用し、個人の事情に応じて、柔軟に修業年限を超えて履修を行い、国家資格や学位の取得をめざせる学び方となります。すべての学年を対象としており修業年限にかかわらず学費の総額は変わらず、学びやすさにつながります。
- 資料請求カートに追加(送料とも無料)
- 資料請求キャンペーン対象
-
 私立短期大学 | 愛知県
私立短期大学 | 愛知県愛知学院大学短期大学部
専門知識と寄り添う心で、歯の健康を守る歯科衛生士へ
1876年に曹洞宗専門学支校として歩み始めた愛知学院では、常に時代の要請に応えながら社会に貢献できる人材を育成してきました。本学が創設以来、取り組んできたのは、禅の教えに基づく「人間教育」。一人ひとりの学生と真剣に向き合い、可能性を導き出す教育で、数字では表せない本質的な能力を引き出します。その能力に対する自覚を促し、やる気を引き出し、確かな成長へと学生を導きます。 愛知学院大学短期大学部は、歯科衛生学科と専攻科を設置。歯科衛生学科は、「歯と口腔」の健康を守る歯科衛生士のスペシャリストを育成します。高度な知識・技術はもちろん、歯や口腔の特性や状態を的確に理解し、個人や集団、地域におけるロ腔保健に関する課題や、一人ひとりのライフステージや健康レベルに応じたサポートができる能力を身につけます。 専攻科は、口腔保健学による高度な専門的知識・技能を修得。人々の健康生活を維持する医療従事者としての使命感や倫理観、良好な人間関係を構築できるコミュニケーション能力を養うとともに、学士の学位取得を目指すことができます。 本学は時代が求める歯科衛生士の育成を追求し続けます。
- 資料請求カートに追加(送料とも無料)
- 資料請求キャンペーン対象
東海・北陸の医学・歯学・薬学・看護・リハビリが学べる私立短大の学校検索結果
4件
1-4件を表示