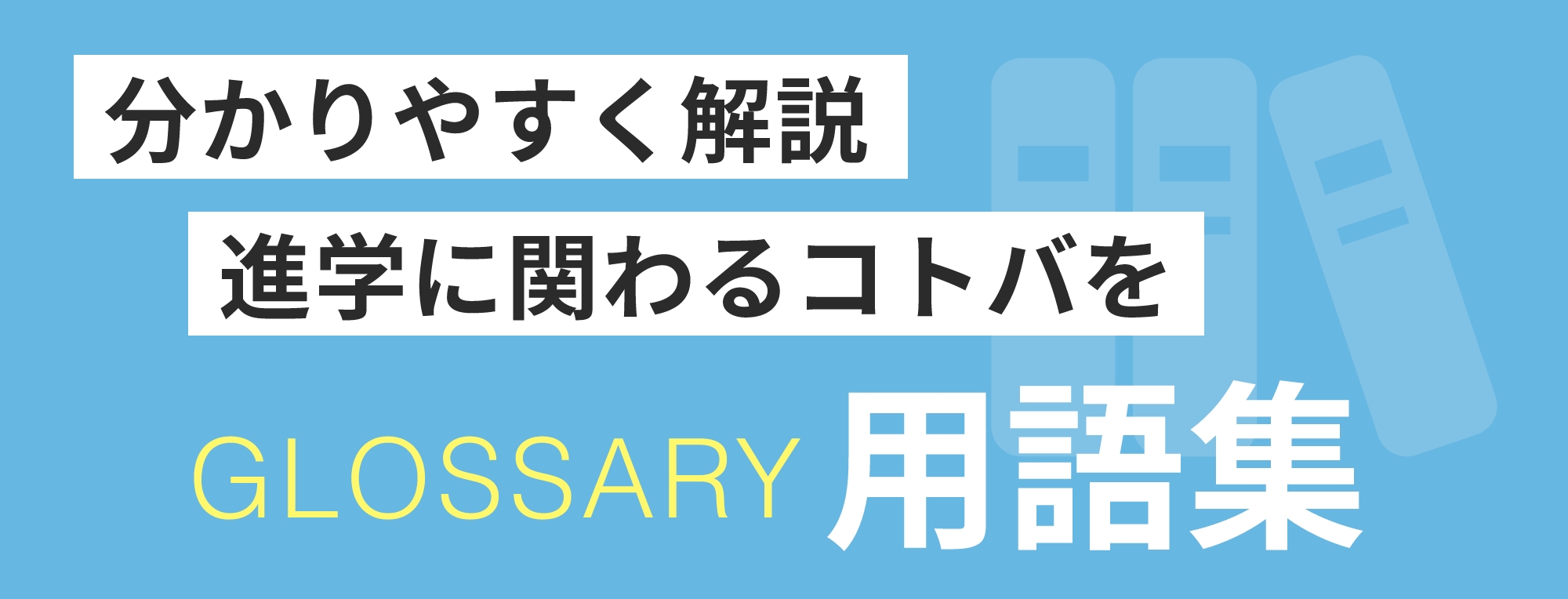理由や根拠を示しながら自分の意見や主張を述べる小論文
そもそも小論文とはどのような文章でしょうか? これまでに書いてきた作文とはどう違うのでしょうか? 一般的に、自分の体験や感想を表現力豊かに書く作文に対し、自分の意見や主張とその理由を論理的に述べるのが小論文です。作文に比べて、自分で問題を発見する力や考える力、説得力が求められます。入試で出題される場合、出題の形式や内容は多様です。特定のテーマが与えられる場合は、時事問題など一般的なテーマから専門分野に関するテーマまでさまざま。また、長文の課題文や表・グラフなどの資料を読み解くタイプもあれば、志望理由や自分の興味・関心のあることについて書く場合もあります。