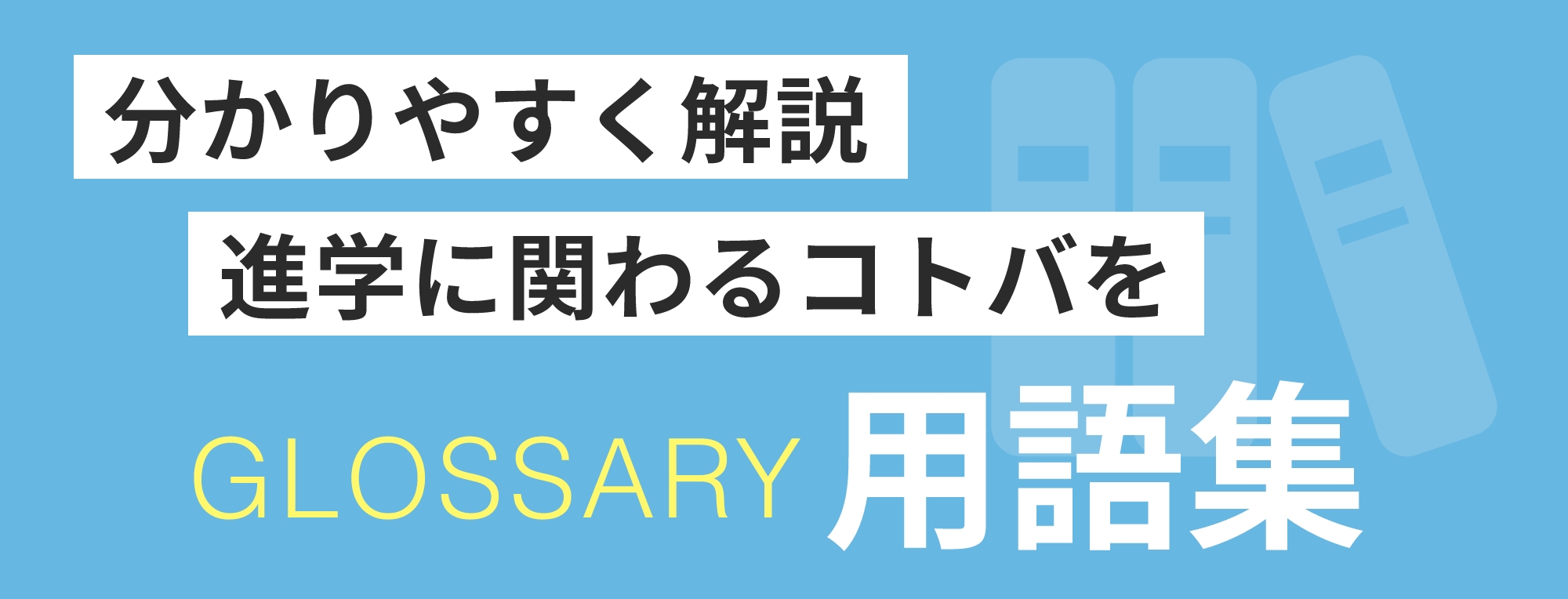「自分」をアピールして志望校へ
私立大学のほとんどが実施している総合型選抜は、大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)に合う人物を採用するための入試です。求める人物像は大学・学部学科によってさまざまで、「リーダーシップがある」「新しい環境に挑戦する意欲がある」など資質や個性について定められている場合もあれば、特定の技術や資格、海外経験などが求められる場合もあります。 総合型選抜は高校からの推薦が必要ないため、条件を満たせば誰でも出願でき、志望校に直接熱意をアピールすることができます。選考では「求める人物像と合っているか」「入学への強い意欲があるか」「大学・学部学科のことをよく理解しているか」「入学後の明確な目標があるか」などが重視され、大学・学部学科にふさわしいかが審査されます。