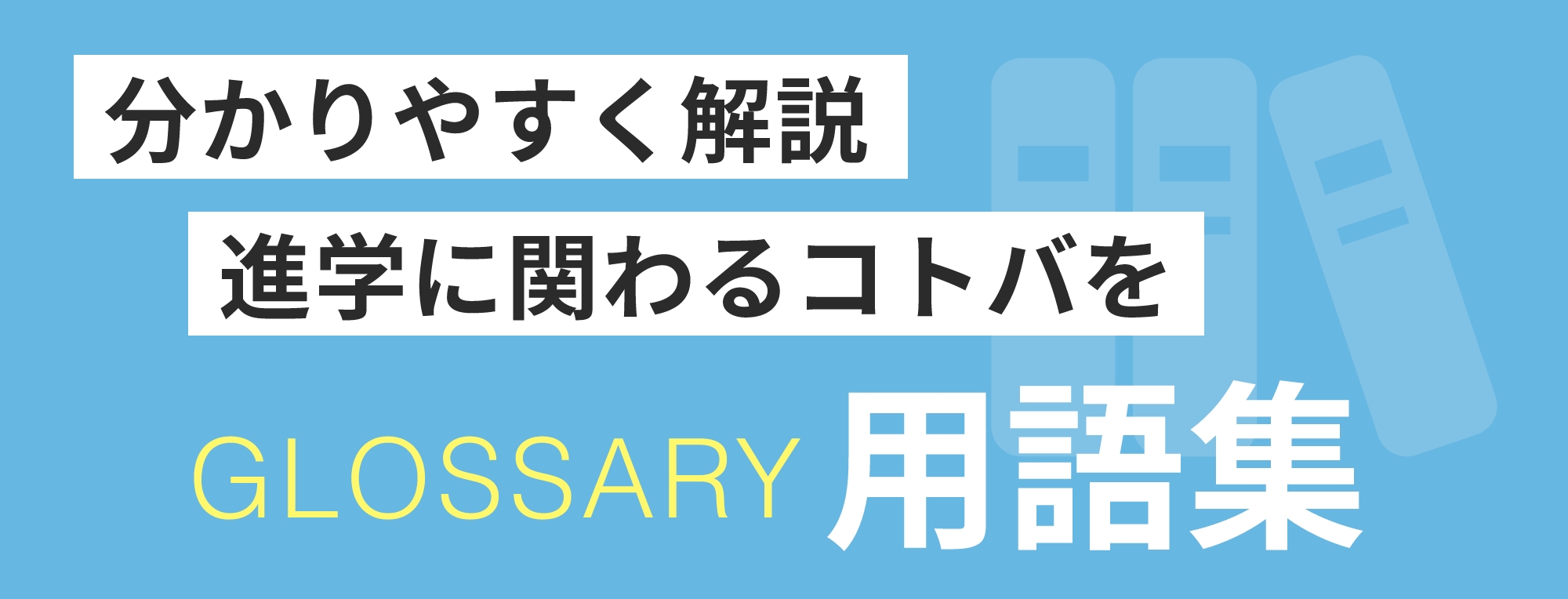大学全入時代の特徴
少子化にともない、大学入試を受験する18歳の人口が1992(平成4)年をピークに著しく減少しています。大学進学者が増える一方、18歳人口が低下することによって、えり好みしなければ全員が大学に入学できるという現象が起こるようになりました。このことは一般的には「大学全入時代」と呼ばれています。
私立大学の定員割れは、2000年代に入ってから著しく増加しています。入学定員の充足率が100%未満の私立大学は、2022年度において284校、全体の47.5%にのぼりました(※)。つまり4割以上の私立大学において、入学者が定員に満たない現象が起こっています。そうした状況を踏まえ、各大学は入学生の確保に向けて、多様な個性や資質をそなえた学生を選抜する入試(下記「人物重視の入学試験」参照)を行うようになりました。
※参考:日本私立学校振興・共済事業団「令和4(2022)年度私立大学・短期大学等入学志願動向」